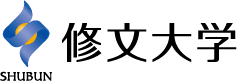NURSING FACULTY
CURRICULUM
看護学部 カリキュラム
カリキュラム
大学教育として体系化された学びを積み上げることで、高い専門性と実践力を身につけることができます。
1年次
黒文字は必修科目、赤文字は必修科目
※2024年度のカリキュラムです。(参考)
- 基礎分野
- 専門
基礎分野 - 専門分野
人間と文化
言語と表現 / 家族社会学 / 心理学 / 生命倫理
生活美学 / 教育学 / 音楽 / 哲学 / 国際文化論 / 食文化論
自然と社会
日本国憲法 / 化学
ジェンダー論 / 暮らしと経済 / 生物学 / 物理学
統計学
コミュニケーション
ナーシングイングリッシュⅠ / ナーシングイングリッシュⅡ
中国語 / フランス語 / ドイツ語 / 手話 / コミュニケーション論 / カウンセリング論
総合
基礎ゼミナール / 情報科学 / 情報科学演習
健康運動スポーツ科学論 / 健康運動スポーツ実技
2年次
黒文字は必修科目、赤文字は必修科目
※2024年度のカリキュラムです。(参考)
- 基礎分野
- 専門
基礎分野 - 専門分野
- 保健師課程
自然と社会
データサイエンス演習
コミュニケーション
ナーシングイングリッシュⅢ
3年次
黒文字は必修科目、赤文字は必修科目
※2024年度のカリキュラムです。(参考)
- 基礎分野
- 専門
基礎分野 - 保健師課程
健康障害と回復
臨床栄養学
健康支援と社会制度
社会福祉学 / 保健統計学
4年次
黒文字は必修科目、赤文字は必修科目
※2024年度のカリキュラムです。(参考)
- 専門分野
- 保健師課程
統合看護
災害看護学 / 看護研究方法Ⅲ / 看護特論
臨地実習
地域・在宅看護学実習 / 急性期看護学実習 / 慢性期看護学実習 / 老年看護学実習 / 小児看護学実習 / 母性看護学実習 / 精神看護学実習 / 統合看護実習
看護の専門8領域
本学では8つの専門領域を設けており、看護職者に必要とされる知識と技術を専門領域ごとに系統的に修得します。
-
1.基礎看護学

看護職者として必要な
看護の基礎を学ぶ。「国家・社会に貢献できる人材の育成」という建学の精神に基づき、社会に有為な人材の育成に取り組んでいます。
-
2.成人看護学

成人期の特性を理解し
看護実践能力の向上をめざす。成人期の健康障害を抱える対象者とその家族の特徴を理解し、急性期、慢性期、終末期にある人々の看護を学修します。
-
3.母性看護学

周産期、育児期の看護を極める。
妊娠・分娩・産褥・新生児期における母子とその家族を対象とした看護と、女性の生涯にわたる健康の保持・増進に関する看護を学修します。
-
4.小児看護学

小児と家族のQOL向上をめざす。
小児期にある対象者の発達特性を踏まえた小児特有の疾患を理解し、こどもとその家族が抱える健康問題に対してQOLを尊重した看護を学修します。
-
5.老年看護学

高齢者の尊厳と自律の配慮をめざす。
老年期にある対象者の身体的状況、精神的状況、家族を含めた社会的状況や生活基盤を見つめながら、高齢者の尊厳と自律に配慮した看護を学びます。
-
6.地域・在宅看護学

生活の場で提供する看護を学ぶ。
在宅で療養する人々やその家族を"地域で生活する人"と捉え、その人の暮らしを理解して、その人の望む暮らし方を支える看護を学修します。
-
7.精神看護学

心の健康維持・増進への看護を学ぶ。
複雑化する社会情勢の中で、対象者が抱えている生きにくさを理解し、精神疾患の看護だけでなく、看護のあらゆる領域の対象者の心の健康維持・増進への看護を学修します。
-
8.公衆衛生看護学

保健師の専門性を学ぶ。
公衆衛生看護の基本理念を理解し、地域のあらゆるライフステージ、健康レベルにある人々を対象に、健康を守るための活動を支援する保健師の専門性と支援方法について学修します。